コーティング材の目的
鋼管の外面コーティングは、錆の発生を防ぐために不可欠です。鋼管表面の錆は、その機能、品質、そして外観に重大な影響を与える可能性があります。したがって、コーティングプロセスは鋼管製品全体の品質に大きな影響を与えます。
-
コーティング材料の要件
アメリカ石油協会(API)の基準では、鋼管は少なくとも3ヶ月間の耐腐食性が必要です。しかし、より長い防錆期間への需要が高まっており、多くのユーザーは屋外保管条件において3~6ヶ月間の耐腐食性を求めています。長寿命という要件に加え、ユーザーはコーティングが滑らかな表面を維持し、防錆剤が均一に分散され、外観を損なうような飛散や垂れがないことを期待しています。

-
コーティング材の種類とその長所と短所
都市の地下パイプネットワークでは、鋼管ガス、石油、水などの輸送にますます利用されるようになっています。これらのパイプのコーティングは、従来のアスファルト材からポリエチレン樹脂やエポキシ樹脂材へと進化してきました。ポリエチレン樹脂コーティングの使用は1980年代に始まり、用途の多様化に伴い、その構成部品とコーティングプロセスは徐々に改良されてきました。
3.1 石油アスファルトコーティング
従来の防錆層である石油アスファルトコーティングは、石油アスファルト層をガラス繊維布で補強し、外側にポリ塩化ビニル保護フィルムを塗布した構造です。優れた防水性、様々な表面への密着性、そしてコスト効率の良さを特徴としています。しかし、温度変化の影響を受けやすく、低温下では脆くなり、特に岩石質土壌では経年劣化やひび割れが発生しやすいという欠点があり、追加の防錆対策とコスト増加を招きます。
3.2 コールタールエポキシコーティング
エポキシ樹脂とコールタールアスファルトから作られるコールタールエポキシは、優れた耐水性、耐薬品性、耐腐食性、良好な接着性、機械的強度、絶縁性を備えています。しかし、塗布後の硬化時間が長く、その間の気象条件の影響を受けやすいという欠点があります。さらに、このコーティングシステムに使用される様々な成分は専用の保管場所を必要とするため、コストが高くなります。
3.3 エポキシ粉体塗装
1960年代に導入されたエポキシ粉体塗装は、前処理・予熱されたパイプ表面に粉体を静電噴霧することで、緻密な防錆層を形成するものです。その利点は、広い温度範囲(-60℃~100℃)、強力な接着性、優れたカソード剥離耐性、耐衝撃性、柔軟性、溶接部損傷耐性などです。しかし、塗膜が薄いため損傷を受けやすく、高度な製造技術と設備が必要となるため、現場での適用には課題が伴います。多くの点で優れているものの、耐熱性と総合的な防錆性に関してはポリエチレンに劣ります。
3.4 ポリエチレン防錆コーティング
ポリエチレンは、優れた耐衝撃性と高い硬度に加え、広い使用温度範囲を備えています。特に低温下における優れた柔軟性と耐衝撃性により、ロシアや西ヨーロッパなどの寒冷地域ではパイプライン用途として広く使用されています。しかし、大口径パイプへの適用には依然として課題が残っており、応力割れの発生や、浸水によるコーティング下地の腐食といった問題が発生する可能性があるため、材料および適用技術の更なる研究と改良が求められています。
3.5 重防錆コーティング
重防食コーティングは、標準的なコーティングに比べて大幅に優れた耐食性を備えています。過酷な環境下でも長期的な効果を発揮し、化学薬品、海洋、溶剤環境では10~15年以上、酸性、アルカリ性、塩分を含む環境では5年以上の耐用年数を有します。これらのコーティングは、乾燥膜厚が通常200μm~2000μmで、優れた保護性能と耐久性を実現します。海洋構造物、化学装置、貯蔵タンク、パイプラインなど、幅広い用途に使用されています。
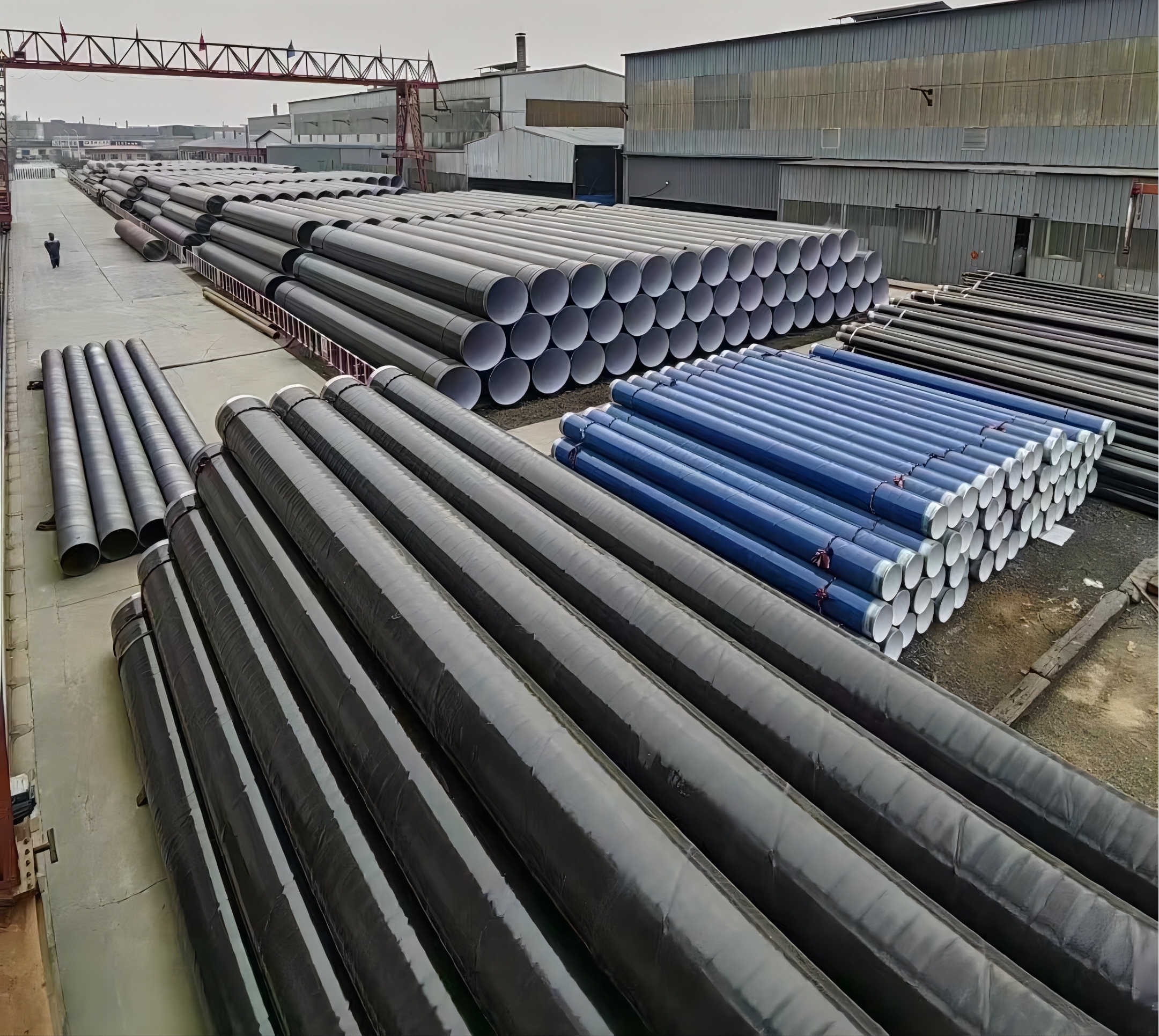
-
コーティング材に関する一般的な問題
コーティングに関する一般的な問題としては、塗布の不均一、防錆剤の垂れ、気泡の発生などがあります。
(1)コーティングの不均一性:パイプ表面に防錆剤が不均一に塗布されると、コーティングが厚すぎる部分が生じて無駄になり、コーティングが薄い部分やコーティングされていない部分はパイプの防錆能力を低下させます。
(2)防錆剤の滴下:防錆剤が配管表面で液滴状に固化する現象で、耐食性には直接影響しないものの、美観に影響を与える。
(3)気泡の発生:防錆剤塗布時に内部に閉じ込められた空気がパイプ表面に気泡を発生させ、外観とコーティング効果の両方に影響を与えます。
-
コーティング品質問題の分析
あらゆる問題は様々な原因から発生し、様々な要因によって引き起こされます。品質上の問題が顕著な鋼管束の場合、複数の要因が複合的に影響している可能性があります。塗装ムラの原因は大きく分けて2種類あります。1つは鋼管が塗装ボックスに入った後にスプレー塗装を行うことで発生するムラ現象、もう1つは未スプレー塗装によって発生するムラ現象です。
最初の現象の原因は明白で、塗装設備において鋼管を塗装ボックス内に投入する際、合計6基のガン(ケーシングラインには12基のガン)が360°全周に防錆剤を噴射します。各ガンからの噴射流量が異なると、鋼管の様々な表面において防錆剤が不均一に分布することになります。
2つ目の理由は、スプレー噴射以外にも、塗布ムラが発生する原因が複数あることです。鋼管の錆や粗さなど、様々な要因が考えられます。これらの要因により、塗布が均一に行われにくくなります。また、鋼管表面には乳剤塗布時に残留する水圧痕があり、この際に塗布液が乳剤と接触するため、防腐剤が鋼管表面に付着しにくくなります。その結果、鋼管表面に乳剤が付着せず、鋼管全体に均一に塗布されないという事態も発生します。
(1)防錆剤垂れの原因。鋼管の断面は円形であるため、防錆剤を鋼管表面に噴霧するたびに、上部と端部の防錆剤が重力の影響で下部に流れ、垂れ下がり現象が発生します。幸いなことに、鋼管工場の塗装生産ラインにはオーブン設備があり、鋼管表面に噴霧された防錆剤を適時に加熱固化し、防錆剤の流動性を低下させることができます。しかし、防錆剤の粘度が高くない場合、噴霧後に適切なタイミングで加熱しない場合、加熱温度が高くない場合、ノズルの作動状態が悪い場合など、防錆剤垂れが発生します。
(2)防錆剤の発泡の原因。作業現場の空気湿度が高いため、塗料の分散が過剰になり、分散プロセスの温度低下が防錆剤の発泡現象を引き起こします。空気湿度の高い環境では、低温条件で噴霧された防錆剤が微細な液滴に分散し、温度低下を引き起こします。温度低下後、湿度の高い空気中の水分が凝縮して微細な水滴となり、防錆剤と混ざり合い、最終的に塗膜内部に入り込み、塗膜の膨れ現象を引き起こします。
投稿日時: 2023年12月15日
